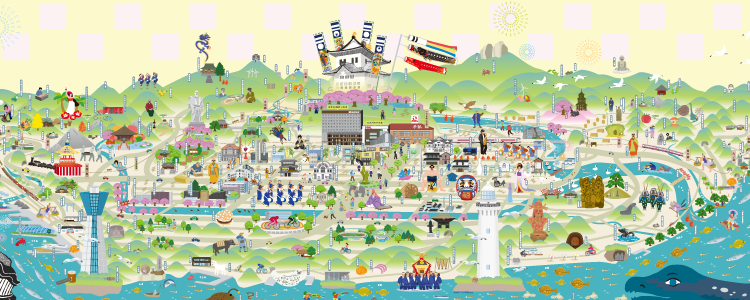石炭・化石館ほるる[せきたんかせきかんほるる] 常磐
歴史・観光・行楽
常磐炭田が繁栄した当時の資料や市内で発見されたフタバスズキリュウをはじめとする貴重な化石が展示されており、模擬坑道では炭鉱の生活や歴史が再現されている。
出典元:公式サイト
背戸峨廊[せどがろ] 小川
歴史・観光・行楽
夏井川渓谷の支流の一つである江田川を指し、奇岩怪石と大小10以上もの滝が続き、激しい流れと瀞が変化に富んだ景色を作り出している。命名はかえるの詩人・草野心平による。
出典元:いわき市観光サイト
専称寺[せんしょうじ] 平
歴史・観光・行楽
浄土宗のお寺。境内には約500本の梅があり、東北地方の梅の名所としても知られている。本堂・庫裏・総門が国の指定重要文化財となっている。
出典元:いわき市観光サイト
象パレード[ぞうパレード] 平
伝承・伝説
昭和27年、上野動物園のゾウが平駅前通りをPR行進。市営グラウンド(平第一小学校)で得意な芸を披露した。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
相馬野馬追[そうまのまおい] 南相馬市・相馬市
歴史・観光・行楽
千年以上前、相馬氏の祖といわれている平将門が下総国(千葉県北西部)に野馬を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行ったのが始まりと伝えられ、現在では、毎年7月末の土曜日・日曜日・月曜日、甲冑に身を固めた総勢約400騎の騎馬武者が腰に太刀、背に旗指物をつけて疾走する豪華絢爛で勇壮な時代絵巻を繰り広げる。お行列、甲冑競馬、神旗争奪戦、神事・野馬懸などが3日間に渡って行われる。
出典元:南相馬市観光情報サイト
SONIC(club SONIC iwaki)[そにっく(くらぶそにっくいわき)] 平
歴史・観光・行楽
かつて映画館だった建物を改装したライブハウス。アコースティックからラウド系まで幅広いジャンルに対応。地元のライブシーンの底辺を支え続けている。
出典元:公式サイト
染工場[そめこうば] 平
特産品・土産
江戸時代は紺屋町が染物の中心地であった。現在、五丁目にも染工場があり、祭りで使用される法被などの染めを担っている。
大黒屋[だいこくや] 平
伝承・伝説
福島県浜通り地方の唯一の百貨店として、街での買い物やお中元・お歳暮などの贈り物、 衣類の仕立てなど、大黒屋ブランドを築き上げ、親しまれてきた。2001年に閉店。
袋中上人[たいちゅうしょうにん] 平
人物
1552年、現在のいわき市常磐西郷町出身の、浄土宗の学僧。傑出した才能を持ち遊学ののち浄徳寺住職を経て菩提院を開山。岩城氏改易を機に、求法のため渡明を志して渡海。ルソン等を旅するものの入明は果たせず琉球に渡り、初めて念仏を琉球に伝える。この念仏がエイサーの源流のひとつとなる。 帰国後、檀王法林寺など京都奈良大坂で多くの寺院を開山・中興した。
大悲山大蛇伝説[だいひさだいじゃものがたり] 南相馬市
伝承・伝説
目の見えない琵琶法師・玉都は目を治すため、小高の大悲山薬師堂で願をかけていた。武士が現れその音色に聞き入るが、その武士は池に住む大蛇だった。小高に大雨を降らせ大沼にするという大蛇の言葉を小高城の殿に訴えた玉都はさらわれてしまうが、玉都の訴えのおかげで小高の陣営は大蛇を退治することができた。
出典元:小高観光協会HP
太平桜酒造[たいへいさくらしゅぞう] 湯長谷
特産品・土産
創業は1725年(享保10年)。江戸時代から300年続き地元に根付いているいわきの地酒。福島県の酒造好適米「夢の香」や福島県の酒用酵母「うつくしま夢酵母」を使用し、原材料のすべてが福島県産。
平駅[たいらえき] 平
伝承・伝説
明治30年、石炭産業と首都圏をつなぐため日本鉄道磐城線(現JR常磐線)が敷かれ「平駅」が誕生。昭和4年に建て替えられたレトロな建物は昭和40年代まで引き継がれ、老朽化のため建て替えを迫られ、昭和48年に平駅ビル「ヤンヤン」として改築された。
平警察署[たいらけいさつしょ] 平
伝承・伝説
元々宿場町だった「紺屋町」は遊郭が立ち並ぶ地域だったが、明治4年に取り締まりが強化され遊女屋は消えた。その跡に建てられたのが、福島県警察平出張所であった。
平座[たいらざ] 平
伝承・伝説
明治38年11月、平駅前に大きな劇場が誕生した。こけら落としは東京名題歌舞伎の千両役者市川九団次、片岡市蔵一座。それを歌川豊斎が描いた。この東北一の大劇場は年が明けた明治39年2月の平大火で焼失した。わずか三ヶ月たらずだった。
平七夕まつり[たいらたなばたまつり] 平
民俗・芸能
いわき市最大級の夏祭り。七夕飾りが商店街を彩り露店が並ぶ。七十七銀行が七夕飾りを飾り、街に広がった。「平七夕まつり」が始まったのは昭和9年。令和元年に「いわき七夕まつり」
出典元:いわき市観光サイト
高木誠一[たかぎせいいち] 平
人物
明治二〇年、いわき市平北神谷生まれ。篤農家であり郷土研究者。いわき民俗学の祖として柳田國男の民俗学研究にも協力。宮本常一の著書『忘れられた日本人』でも「文字を持つ伝承者」として紹介されている。
鷹匠[たかじょう] 平
伝承・伝説
かつてこのあたりに鷹匠がいた。「鷹匠町」という地名が残っている。
薪能[たきぎのう] 葛尾村
民俗・芸能
江戸時代から明治にかけて葛尾村で栄華を誇った松本三九郎一族の邸宅「葛尾大尽」には当時能舞台があり、能狂言を鑑賞した歴史が残る。2019年に160年振りに葛尾大尽屋敷跡で能・狂言が開催された。
出典元:葛尾むらづくり公社HP