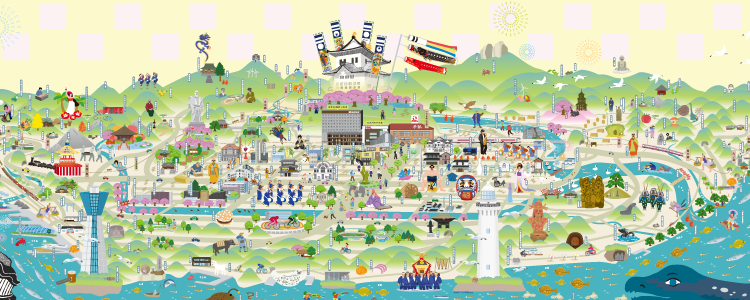神田伯龍[かんだはくりゅう] 平
人物
文政中、紺屋町出身の講談師が寄席を麹町に開き講談を弁じていたという。異色で傑出した人柄と熱弁で聴衆を惹きつけ、高い評価を得ていた。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
狐塚[きつねづか] 四倉
伝承・伝説
北条時頼が東北地方を巡り歩き、四倉で宿をとった時のこと。夜中に狐の声で目を覚まし外に出ると数千もの狐が集まってきて鳴いていた。不憫に思い「なつもきつねになくせみのからころも おのれおのれのゆくすえをみよ」と一句詠むと悲しげな声はぴたりとやんだという。朝になると狐は全て骸となっていた。
出典元:「いわきの伝説」草野日出夫編著
清戸迫横穴[きよとさくおうけつ] 双葉町
歴史・観光・行楽
双葉町立双葉南小学校敷地内に保存されている横穴式装飾古墳。赤色顔料で渦巻文を中心に冠または帽子をかぶった人物2人を配し、その左右に小さく乗馬の人物、弓を射る人、鹿、犬等の動物を描いている。現在判明している彩色壁画の北限である。
出典元:文化遺産オンライン
霧島昇[きりしまのぼる] 大久
人物
戦前から戦後にかけて活躍した流行歌手。本名は坂本 榮吾。福島県双葉郡大久村(現在のいわき市)出身。1979年(昭和54年)紫綬褒章受章。
金冠塚古墳[きんかんづかこふん] 錦
歴史・観光・行楽
直径約28m・高さ約3mの円墳。横穴式石室の中に13体分の人骨のほか金銅製飾金具や玉類、馬具、須恵器などが出土。
草野心平[くさのしんぺい] 小川
人物
1903年に生まれる。蛙の詩人とも言われるが「富士山」「天」「石」等を主題にし、同級生から「機関銃(マシンガン)と呼ばれるほどの多作。貸本屋「天山」、居酒屋「火の車」とその後のバア「学校」等様々な取り組みをしながら、高村光太郎、中原中也など広範な交友関係を持っていた。祖父は白井遠平。
草野心平記念文学館[くさのしんぺいきねんぶんがくかん] 小川
歴史・観光・行楽
いわき市の名誉市民でもある詩人 草野心平(1903~1988年)の生涯と作品の魅力を、自筆原稿、詩集、自作朗読音源、そして彼が開いた居酒屋「火の車」の復元展示などで紹介するほか、文学をはじめとした企画展、講演会、演奏会など、多彩な催しを開催。
出典元:公式サイト
草野心平記念文学館[くさのしんぺいぶんがくかん] 小川
歴史・観光・行楽
草野心平の自筆原稿、詩集、自作朗読音源、居酒屋「火の車」の復元展示など、作品の魅力を紹介。企画展、講演会、演奏会などの様々な企画も開催している。
出典元:公式サイト
鯨[くじら] くじら
伝承・伝説
いわきの海岸を舞台に古式捕鯨の様子を描いた絵巻「紙本著色磐城七浜捕鯨絵巻」が見つかったことから、磐城平藩内藤家の時代にいわきで捕鯨が行われていたことが注目されるようになりました。
出典元:海と日本PROJECT in ふくしま「磐城国 海の風土記 vol.10」
首切り地蔵[くびきりじぞう] 平
歴史・観光・行楽
小川江筋の整備などし100年以上領土を治めてきた磐城平藩・内藤氏であったが財政難に陥り課税を強化。1738年に大規模な百姓一揆が発生し農民2万人が城下に押し寄せた。しかし、訴えは認められず、指導者7人が鎌田河原で処刑。一方で、大規模な百姓一揆の罰として、内藤氏は延岡藩に移封となった。その後、鎌田河原には村人らによって供養のための「首切り地蔵」(河原子地蔵堂)が建てられた。
久保姫[くぼひめ] 平
人物
岩城重隆の長女。奥州一の美少女として名高く、嫁ぎ先をめぐっては伊達氏や相馬氏と対立し、白河城主・結城氏のもとへ嫁入りが決まり輿入れの道中、久保姫の美しさに一目ぼれした伊達晴宗が襲撃し姫を略奪するという顛末に。ところが夫婦となった2人は仲が良く、第一子を岩城家の養子にすることを条件に和解した。
クマガイソウ群生地[くまがいそう] 田人
歴史・観光・行楽
田人町石住綱木にある約5万株のクマガイソウの群生地。日本最大級とも言われている。近年、絶滅危惧種であるクマガイソウ。守る会が発足し、手入れや環境整備などをおこなっている。例年5月上旬から咲き始め、下旬ごろまで楽しむことができる。
出典元:いわき市観光サイト
熊見温泉[くまみおんせん] 内郷
伝承・伝説
石炭の採掘の際に生じた温泉水の排湯口の集約工事が昭和32年2月に完了し、新川に設置された送湯管からは摂氏46度のお湯が滝のように川に注ぐことになった。川岸に脱衣小屋が次々と建てられ話題になり「クマミ温泉」として人気を集めた。その後、様々な理由により昭和33年7月に撤去命令。昭和34年秋には姿を消した。
出典元:いわきの『今むがし』
暮らしの伝承郷[くらしのでんしょうごう] 鹿島
歴史・観光・行楽
市内に残っていた茅葺の古民家を移築し、建築当初の状態を復元して展示。年中行事の再現や伝統芸能の実演など、昔の人々の暮らしを今に伝える。
出典元:いわき市観光サイト
芸妓[げいこ] 平
伝承・伝説
平芸妓屋は今の揚土付近からはじまった。名妓「小春」「小勝」など名の残る芸妓もおり、大正五年には一六八名を数えたという。明治の頃は、若い芸妓はつぶし島田、年増芸妓はいちょう返しと、時代の移り変わりと共に花街情緒を作り出していた。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
芸術文化交流館アリオス[げいじゅつぶんかこうりゅうかんアリオス] 平
歴史・観光・行楽
いわき市民の多様な文化・芸術・交流活動の拠点。様々な機能を兼ね備えたホールや稽古場を整備した施設。敷地内には平中央公園があり、市民の憩いの場となっている。
出典元:いわき市観光サイト
考古資料館[こうこしりょうかん] 常磐
歴史・観光・行楽
古代を感じ、体験し、学習できる資料館。 いわき市内の遺跡から出土した約1,500点の土器などを展示。勾玉や埴輪づくりなど、体験学習も開催。
出典元:いわき市観光サイト
国産奨励大博覧会[こくさんしょうれいだいはくらんかい] 平
伝承・伝説
大正14年、大正デモクラシーの波に乗って西欧文化がもてはやされていた時代、国産品を見直そうと訴えた大博覧会。専売特許のメイドインジャパンの新発明品が陳列・披露され、大変な賑わいようだったという。飛行機からチラシをばら撒くという驚きの宣伝がなされ、地元産業の振興にも大きな役割を果たした。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
国宝・白水阿弥陀堂[こくほう・しらみずあみだどう] 内郷
歴史・観光・行楽
藤原清衡の娘・徳姫が、夫 岩城則道公の供養のために建立したといわれる平安時代後期の代表的な阿弥陀堂建築。美しい曲線を描く屋根と浄土式庭園が調和した優美な姿を見せてくれ、秋には大イチョウやモミジなどが庭園を美しく彩る。 福島県では建造物として唯一国宝に指定されている。
出典元:いわき市観光サイト