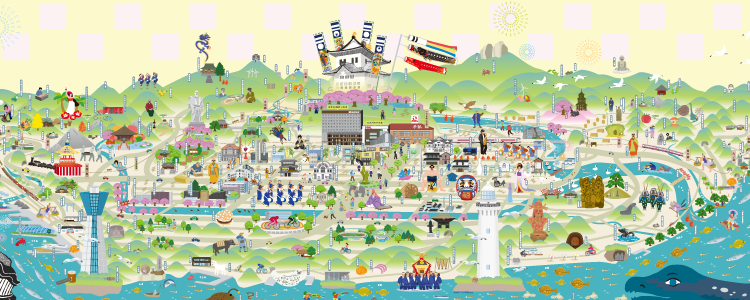子鍬倉神社[こくわくらじんじゃ] 平
歴史・観光・行楽
平城守りの神「平城三社」の一つ。明治6年(1873年)3月に「県社」に列格した。昭和21年近代社格制度廃止の後も「けんしゃ」の愛称。
出典元:いわき市観光サイト
凍み餅[こごみもち] 広域
特産品・土産
「ごんぼっぱ」(山ごぼう)ともち米とうるち米の粉を混ぜたものを蒸し餅にして型に入れ固め、それを切って寒風にさらして干した保存食
金刀比羅神社[ことひらじんじゃ] 湯本
歴史・観光・行楽
500年の歴史を持ち、大物主大神(オオモノヌシノカミ)を御祭神とする神社。毎年1月10日の例大祭は「初こんぴら」とも言われ、海上安全、商売繁盛を願い、福だるま(いわきだるま)や熊手を買い求める人で賑わう。
出典元:いわき市観光サイト
こどもの村[こどものむら] 四倉
伝承・伝説
体育館、ゴーカート、卓球、野球、小さな動物園、バンガロー、アスレチック、ローラースケート場、などもあったという。
差塩湿原[さいそしつげん] 三和
歴史・観光・行楽
海抜500mにある低層湿原で、今から約2万年前の洪積世の最終氷河期にできたとされている。5月頃に開花するミツガシワは氷河期からの生き残りといわれ、市の天然記念物に指定されている。
出典元:いわき市観光サイト
賽の河原[さいのかわら] 平
歴史・観光・行楽
海沿いにある洞窟が水子供養の霊場となり、多くのお地蔵様が置かれていた。洞窟の崩落が進み、現在は、高台にある弁天岬にお地蔵様が移され、供養の場となっている。
坂本紙店[さかもとかみてん] 平
歴史・観光・行楽
昭和25年から続く歴史のある文具店。洋紙・和紙、文房具や事務用品も各種取り揃えている。
左義長[さぎちょう] 小浜
民俗・芸能
いわき市小浜海岸に藁をくくりつけた孟宗竹を立てて並べ燃やす盆送り行事。2016年32年ぶりに復活した。波打ち際で燃え盛る火柱が勇壮な景観を作りだし、小浜の夏の風物詩となっている。
鮫川の鮫伝説[さめがわのさめでんせつ] 平・鮫川
伝承・伝説
昔、松川磯に「松川さま」と呼ばれる背に海苔を生やした大鮫が住み、姿を現した時には渚に酒などを捧げていた。ある時、参勤交代帰りの相馬の殿様が、松川様とは知らずに矢を放ち当たってしまった。その数年後、殿様が愛馬に乗って夏井川を渡っていたところ、矢を突き立てた大鮫が襲ってきた。難は逃れたが、愛馬は力尽きて死んでまった。平塩にある馬頭観音はその愛馬を祀ったものだという。
出典元:「いわきの伝説」草野日出夫編著
鮫伝説[さめでんせつ] 鮫川・平
伝承・伝説
「松川さま」とと呼ばれるサメが相馬の殿様の矢にあたり沈んでしまった。その後、殿様が川に差し掛かったときに水飛沫をあげる波とともにサメが川を登ってきて殿様の愛馬が力尽きてしまったという伝説。平の塩地区に馬頭観世音が残る。
出典元:海ノ民話のまちプロジェクト(日本財団)
三匹獅子舞[さんびきししまい] 広域
民俗・芸能
鹿の獅子頭を被り、腰に羯鼓(かっこ)という小太鼓をつけ打ちながら、三頭が一組になって舞う。戦国時代末期から江戸時代にかけて伝わったとされ、市内各所で行われている。
出典元:いわき市観光サイト
さんまのみりん干し[さんまのみりんぼし] 広域
特産品・土産
いわきが発祥といわれている。それまで作っていたイワシのみりん干しに代え、小名浜の安川一郎氏が、サンマを使い始めたのが起源だという。
出典元:いわき常磐もの
Jヴィレッジ[じぇいびれっじ] 楢葉町・広野町
歴史・観光・行楽
日本サッカー界初のナショナルトレーニングセンターとして1997年に開設。2011年3月から2015年6月まで、東日本大震災と原発事故対応のため、自衛隊および東京電力関係者の発電所事故収束に向けての前線基地として利用された。2019年7月グランドオープン。フィールド、スタジアムなどのスポーツ施設のほか、ホテル、レストラン、フィットネスジムも運用している。
出典元:公式HP
塩の道[しおのみち] 中之作
伝承・伝説
江戸時代、阿波国(現在の徳島県)で生産された「斎田塩」がいわき市中之作港で荷揚げされ、中通りや会津に運ばれた。
潮見台[しおみだい] 小名浜
歴史・観光・行楽
三崎公園の敷地内にある展望台。岬の突端から突き出るように建てられ、雄大な太平洋と磯場を楽しめる絶景スポット。
塩屋[しおや] 平
伝承・伝説
天保10年(1839)に塩問屋として創業し繁盛した。その後明治10年(1877)頃、味噌・醤油の醸造元となった。
塩屋埼灯台[しおやさきとうだい] 平
歴史・観光・行楽
全国でも珍しい、登ることのできる灯台。明治32年に点灯を開始。昭和13年の本県北方沖地震でレンガ造りの初代が大破。(旧灯台のレンガが麓に残っている)現在の灯台は2代目。かつて塩屋崎灯台の灯台守を務めた田中績さん、きよさん夫婦は、木下恵介監督の映画「喜びも悲しみも幾歳月」のモデルとなった。
出典元:いわき市観光サイト
四家酒造店[しけしゅぞうてん] 内郷
特産品・土産
1845年、無類の酒好きだった四家又兵衛によって清酒造りが始められた。1936年『福美』が第15回全国酒類醤油品評会で優等賞を受賞。1990年代に『大吟醸 又兵衛』を発売。「又兵衛」は地元に根付いた地酒として親しまれています。
出典元:公式HP