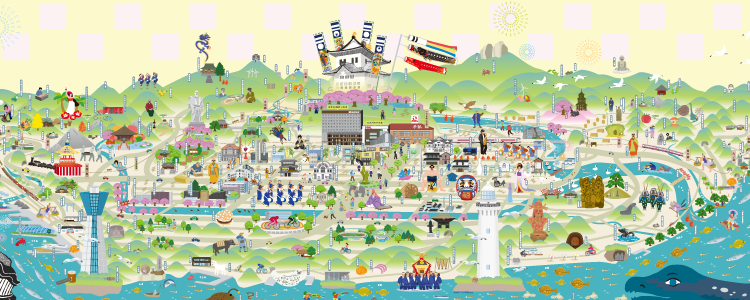みんなの交流館 ならはCANvas[みんなのこうりゅうかんならはきゃんばす] 楢葉町
歴史・観光・行楽
2018年7月開館。全9回のお茶飲みワークショップの中で語られた楢葉町民の想いをもとに設計され、地域や世代を超えて愛される施設を目指している。共有スペース、多目的室、調理室、サウンドルーム、バンドルーム、ワークスペースなどがあり、用途に合わせて利用できる。
出典元:公式HP
木造地蔵菩薩立像鼻取地蔵[もくぞう じ ぞう ぼ さつりゅうぞう] 四倉
歴史・観光・行楽
長隆寺にあり、鎌倉の円覚寺長老から贈られたと伝えられている。この地蔵菩薩が童子の姿となり、田の代かきを手伝ったという鼻取り地蔵の伝説が残っている。
出典元:いわき市観光サイト
モリアオガエル[モリアオガエル] 川内村
歴史・観光・行楽
木の上に卵を産むことで知られるモリアオガエルは日本の固有種。川内村の平伏沼(へぶすぬま)の繁殖地、岩手県八幡平市の大揚沼の繁殖地が国指定の天然記念物と指定されている。伝説では平伏沼を延命の沼とも呼ばれ、樹上のカエルを見れば命が伸びるらしい。
八茎鉱山[やぐきこうざん] 四倉
伝承・伝説
700年台に発見、1500〜1600年代は佐竹氏や平藩により開発が進められ、当時は銅を主に採掘し、日本有数の銅山だったという。森林伐採による水害の影響などで閉山と再開を繰り返したが、タングステンや砕石、石灰石の採掘などが行われてきた。タングステンの生産量は日本一を記録。現在は採掘は行われていない。
八茎薬師[やぐきやくし] 四倉
歴史・観光・行楽
いわきの三大薬師の1つ。大同元年(806年)徳一大師の創建といわれている。以前は山頂にあったが、火災による消失で現在の場所に再建。お堂が鳴動することがあり「鳴堂」とも呼ばれている。
出典元:いわき市観光サイト
谷口楼[やぐちろう] 平
伝承・伝説
明治15(1882)年、天ぷら・うなぎの店として開業。明治から昭和19年まで芸妓を置き、自ら絵はがきを発するほど隆盛を極め、田町が賑やかな時代の料亭文化の中心を担った。
ヤッチキ踊り[やっちきおどり] 三和
民俗・芸能
明治~大正期に九州の炭坑夫が伝えたとの説もあり、いわきの各地で踊られていたが、証言や記録が少なく、調査事例もあまりないことから、不明な点が多い。三和町上三坂の「ヤッチキ踊り」が平成8年に県の「重要無形民俗文化財」に指定された。
出典元:いわきの「いごき」を伝えるウェブマガジン igoku
やっちゃば(鮮場やっちゃば)[やっちゃば(せんばやっちゃば)] 平
特産品・土産
「鮮場やっちゃば」。地元に根ざした新鮮で値段が安いスーパー。青果、鮮魚、精肉、100均が営業している。
八橋検校[やつはしけんぎょう] 平
人物
江戸時代初期、1614年にいわき市で生まれたという説がある。幼い頃から目が不自由だったものの、江戸に出て箏を習い、その後、京にのぼった。1650年頃からは、新しい調弦法を編み出し、「雲井の曲」、「六段の調」、「八段の調」など、数多くの筝曲を作曲し、近代筝曲の開祖と言われた。検校没後、琴に似せた「八ッ橋」という干菓子が発売された。
流鏑馬神事[やぶさめしんじ] 平
歴史・観光・行楽
飯野八幡宮の例大祭で行われる神事。狩装束に身を包んだ騎士が馬場空駆け・生姜撒き・扇子撒き・的矢の順で4度馬を走らせ、生姜撒き・扇子撒きでは縁起物のショウガと扇子がまかれる。
出典元:いわき市観光サイト
山津見神社[やまつみじんじゃ] 飯舘村
歴史・観光・行楽
平安時代、源頼義が白狼に導かれ、凶賊・橘墨虎を捕らえたという伝説にちなんで名付けられた虎捕山の中腹に山津見神社の本殿があり、山の神「大山津見神」を祀っている。2013年に火災で拝殿、狼の天井画などが消失。建物再建後、東京藝術大学の生徒らの協力で231枚の天井画を復元した。
https://www.fsrt.jp/now/no2/4790.html
出典元:福島県/官民合同チームHP
山宗酒造[やまむねしゅぞう] 平
特産品・土産
江戸時代より続く造り酒屋。主な銘柄は、まろやかな「天宅」や淡麗辛口のすっきりとした「閼伽井獄」など。
山村暮鳥[やまむらぼちょう] 平
人物
伝道師として平にきた暮鳥は「真の宗教は芸術なり、偽りなき芸術は宗教なり」とし、同人と共に詩の雑誌を創刊。三野混沌や草野心平との交友もあった。乃木バーの常連だったという。
ヤリイカ[ヤリイカ] 広域
特産品・土産
いわきでも多く水揚げされている。ヤリイカ釣りの船釣りプランも人気。
ヤンヤン[ヤンヤン] 平
伝承・伝説
1973年にオープンした平駅の駅ビル「ヤンヤン」!おみやげ、ファッション、グルメ、カルチャーが集まった場所で、施設名の由来はヤング・ヤングをもじったもの。
祐天上人[ゆうてんしょうにん] 四倉
人物
陸奥国(後の磐城国)磐城郡新田村(上仁井田村、現在のいわき市四倉町上仁井田)に生まれた江戸時代を代表する呪術師。浄土宗大本山増上寺36世法主。
「幽霊橋」(高麗橋)[ゆうれいばし(こうらいばし)] 平
伝承・伝説
399号線の頭上にかかる「高麗橋」。戊辰戦争において同城が落城した際,女性や子供がここから身を投げた,という伝説が残り、高麗橋完成後、自殺が多発する場所と言われ、幽霊の目撃談が多い。大正13年の『常磐毎日新聞』に「幽霊橋の名を高麗橋委員会が命名」という記事が残っているという。