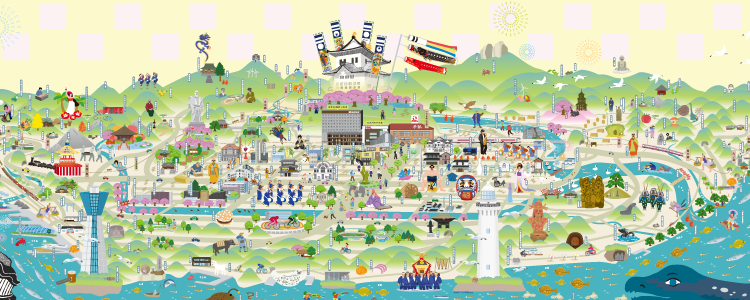湯本温泉[ゆもとおんせん] 湯本
歴史・観光・行楽
いわき湯本温泉は 1300年以上の歴史を持ち、日本の三古泉として名が知られてきた。 中世には戦国大名の来湯、 江戸時代は浜街道唯一の温泉宿場町として人気があった。明治以降、石炭採掘により温泉湧出が止まったものの炭鉱側との協議により復活。炭鉱閉山後は常磐ハワイアンセンター(現・スパリゾートハワイアンズ)のオープンにより名を高めた。泉質はさまざまな効能を併せ持つ。
出典元:いわき市観光サイト
夜明け市場[よあけいちば] 平
歴史・観光・行楽
東日本大震災によって店舗を失ってしまった飲食店オーナーやU・Iターンの人々の事業再生・開業サポートを目指して、白銀小路を改装し、昭和のスナック街だった「白銀小路」を食を通じて盛り上げていこうと始まった飲食街。
出典元:公式サイト
吉野せい[よしのせい] 好間
人物
1899(明治32)年生まれ。詩人の山村暮鳥らの「LE・PRISME」「福島民友新聞」などに短歌や短編を発表。夫は詩人の三野混沌。「洟をたらした神」が1975年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞し、その業績を讃え1978年には「吉野せい賞」が創設された。晩年に農耕生活を送りながら「洟をたらした神」などを執筆した家屋が残っている。
出典元:いわき市観光サイト
夜の森公園[よのもりこうえん] 富岡町
歴史・観光・行楽
小高い丘を有する桜の名所で、樹齢100年以上のソメイヨシノを含むおよそ300本の桜が園内を彩る。原発事故により帰還困難区域に指定されたが、2022年に特定復興再生拠点として立ち入りが緩和され、観桜が可能となった。
出典元:福島県HP
龍燈杉[りゅうとうすぎ] 平
伝承・伝説
樹齢1300年といわれる。昔、乙姫様が難産で大変苦しんだ時に閼伽井嶽の薬師様が助けたことから、乙姫は感謝をしたいと、龍燈を二井田浦から夏井川を遡って、やがて薬師様の下にある龍燈杉の鞘で強い光を放ってから薬師堂に入っていったという伝説がある。
出典元:「いわきの伝説」草野日出夫編著
龍燈伝説[りゅうとうでんせつ] 広域
伝承・伝説
閼伽井嶽に残る伝説。毎晩龍燈が閼伽井嶽の東の海上に発生し、大きな蛍の光のように明滅しながら次々と川を遡り、山を登り、閼伽井嶽まで延々と続いていく。閼伽井嶽からしか見ることは出来ず、我が国を代表する奇観のひとつである(現代語訳一部抜粋)大須賀筠軒が書き残しているという。
出典元:夏井芳徳著「いわきの伝説ノート」
龍門寺[りゅうもんじ] 平
歴史・観光・行楽
応永17年頃に建立。岩城の国主岩城家の菩提寺。茅葺の山門は、いわき市指定文化財となっている。また、龍門寺の井戸と沼の内の賢沼は繋がっているといわれている。
出典元:いわき市観光サイト
六十枚橋[ろくじゅうまいばし] 平
歴史・観光・行楽
説1:豪雨で赤大根が畑から流され、下流の人々がそれを拾い刻んで切干しとしてむしろに干し、六十枚のむしろが並んだ。 説2:江戸へ送る米を小名浜の港に運ぶため夏井川に橋をかけたら、板が60枚必要だった。 説3:平城があった時代、小川で焼いた瓦を夏井川を伝って運んでいた。その瓦の包の単位か数を表したもの。
六角堂[ろっかくどう] 北茨城
歴史・観光・行楽
岡倉天心が明治36年に茨城県の北茨城市大津町にある五浦に訪れ、この地をいたく気に入り、思索の場所として自ら設計したもの。中国、インド、日本といったアジアの伝統思想が、ひとつの建物全体で表現され、世界への発信拠点とした。
ワンダーファーム[ワンダーファーム] 四倉
歴史・観光・行楽
全国でも珍しいトマトのテーマパーク。いわきサンシャイントマトというブランドトマトで有名。トマト狩りや併設のレストランなどが楽しめ、イベントも多く開催されている。
出典元:公式サイト