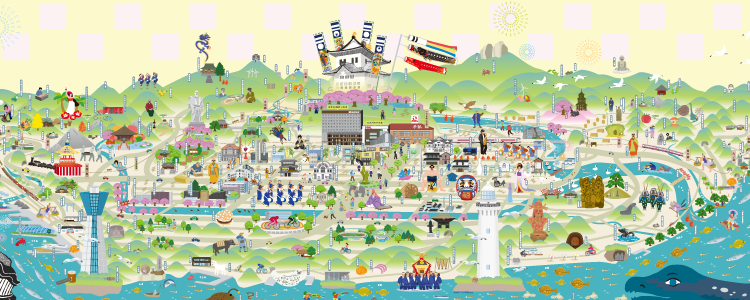夏井川のサケ[なついがわのさけ] 平
伝承・伝説
秋になると海口から鮭の群れがのぼってくるので、今の鎌田橋付近で町の人々は簗場を仕掛け、秋の味覚を楽しんだという。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
仁井田浦[にいだうら] 四倉
伝承・伝説
仁井田川の河口付近、太平洋を望む白砂青松の風景は昭和5年に日本百景に選ばれたこともあり、腰弁当を持参して清遊する人々で賑わったという。ボートを楽しむ憩いの場ともなっていた。
出典元:いわき市観光サイト
乃木バー[のぎばー] 平
伝承・伝説
大正になるとバーという言葉が登場し、平の街中に「乃木バー」という西洋料理店が開店した。「廉価と簡便が同店の特色、西洋料理も酒類も他の洋食店よりは5銭乃至10銭方安価である、経営者の鈴木七十一君は年若い青年であるだけ総てか現代的に清新の気に満ちて居る」(大正8年「いはらき」)という記事も残る。
出典元:歴史春秋社 おやけこういち いわき発 歳月からの伝言2
原町無線塔[はらまちむせんとう] 南相馬市
伝承・伝説
1921年、アメリカとの無線通信のため建てられた電波送信塔。高さ約200メートルで、当時はアジア1の高さを誇った、。1923年9月には、関東大震災の第1報をアメリカに伝えたが、1933年に廃所。1982年に老朽化によって取り壊された。
出典元:南相馬市HP
風船爆弾[ふうせんばくだん] 勿来
伝承・伝説
手すき和紙をコンニャク糊で何層にも張り合わせた気球に焼夷弾を吊るした、無人の兵器。日本の戦況劣勢を打開し、戦局の好転を図ろうとして立てられた秘密作戦で、「ふ号作戦」と呼ばれた。
フタバスズキリュウ[ふたばすずきりゅう] 大久
伝承・伝説
大久町入間沢の大久川河岸で、当時高校生だった鈴木直によって化石が発見されたことから、発見者の苗字と発見された地層の「双葉」層群から名付けられた。ドラえもん のび太の恐竜のピー助のモデル。
出典元:ウィキペディア
ブルボン[ブルボン] 平
伝承・伝説
伝説の喫茶店。故宮崎甲子男氏の作品群が大量に鎮座し、そのエネルギッシュな彫刻や作品が独特の世界観を作り出している。
プレイランドぺぴー[プレイランドぺぴー] 平
伝承・伝説
旧常磐炭礦平火力発電所の跡地に作られ平成元年〜五年まで存在した幻の遊園地。観覧車やミニコースター、アイススケート場もあり、“風の子”をイメージして誕生したマスコットキャラクター「ペピーちゃん」がいた。閉園後、使用された電動遊具は大久町の市海竜の里センターに移設され市民に親しまれてきたが、2023年に解体が発表された。
へそ石[へそいし] 江名・永崎
伝承・伝説
江名と永崎の境あたりに臍(へそ)によく似た石がある。この石は時々浮気を起こして出歩くことがあり、石が出歩くと災いが起こると言われていた。昭和39年、浮気をしないようセメントで底辺を接着されたが、年月とともに砂に埋もれて見えなくなっていた。震災後に再び出現し、現在またセメントで固着されている。
盆の迎え火[ぼんのむかえび] 平
伝承・伝説
「一度来てみな いわきの平へ まちは火の海 じゃんがら踊り」と昭和7年頃に盛んに作られた新民謡の流れで作られた「平小唄」の歌詞にあるように、七夕祭り以前、盆の迎え火といえば、江戸時代から続く伝統の盆行事だった。
出典元:未来へつなぐ「いわき」ものがたり いわき市市政施行50周年記念誌
松崎商店[まつざきしょうてん] 平
伝承・伝説
明治39年2月18日、平目抜き通りを襲った大火をきっかけに、火事で焼けない蔵づくりの店舗が作られるようになった。最初に完成したのが松崎商店。陶器や洋酒、砂糖、紙、缶詰などの卸商として店を張っていたという。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
八茎鉱山[やぐきこうざん] 四倉
伝承・伝説
700年台に発見、1500〜1600年代は佐竹氏や平藩により開発が進められ、当時は銅を主に採掘し、日本有数の銅山だったという。森林伐採による水害の影響などで閉山と再開を繰り返したが、タングステンや砕石、石灰石の採掘などが行われてきた。タングステンの生産量は日本一を記録。現在は採掘は行われていない。
谷口楼[やぐちろう] 平
伝承・伝説
明治15(1882)年、天ぷら・うなぎの店として開業。明治から昭和19年まで芸妓を置き、自ら絵はがきを発するほど隆盛を極め、田町が賑やかな時代の料亭文化の中心を担った。
ヤンヤン[ヤンヤン] 平
伝承・伝説
1973年にオープンした平駅の駅ビル「ヤンヤン」!おみやげ、ファッション、グルメ、カルチャーが集まった場所で、施設名の由来はヤング・ヤングをもじったもの。
「幽霊橋」(高麗橋)[ゆうれいばし(こうらいばし)] 平
伝承・伝説
399号線の頭上にかかる「高麗橋」。戊辰戦争において同城が落城した際,女性や子供がここから身を投げた,という伝説が残り、高麗橋完成後、自殺が多発する場所と言われ、幽霊の目撃談が多い。大正13年の『常磐毎日新聞』に「幽霊橋の名を高麗橋委員会が命名」という記事が残っているという。
龍燈杉[りゅうとうすぎ] 平
伝承・伝説
樹齢1300年といわれる。昔、乙姫様が難産で大変苦しんだ時に閼伽井嶽の薬師様が助けたことから、乙姫は感謝をしたいと、龍燈を二井田浦から夏井川を遡って、やがて薬師様の下にある龍燈杉の鞘で強い光を放ってから薬師堂に入っていったという伝説がある。
出典元:「いわきの伝説」草野日出夫編著
龍燈伝説[りゅうとうでんせつ] 広域
伝承・伝説
閼伽井嶽に残る伝説。毎晩龍燈が閼伽井嶽の東の海上に発生し、大きな蛍の光のように明滅しながら次々と川を遡り、山を登り、閼伽井嶽まで延々と続いていく。閼伽井嶽からしか見ることは出来ず、我が国を代表する奇観のひとつである(現代語訳一部抜粋)大須賀筠軒が書き残しているという。
出典元:夏井芳徳著「いわきの伝説ノート」