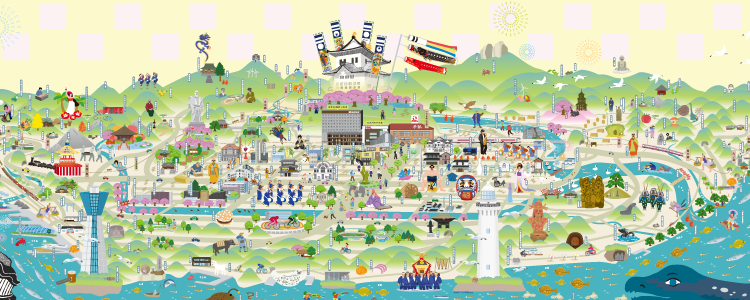小名浜駅[おなはまえき] 小名浜
歴史・観光・行楽
福島臨海鉄道の貨物駅。東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受け、2015年に約600メートル西側に新しい駅舎を建て営業開始。旧駅跡地には防災機能を備えたショッピングセンター(イオンモール)が建設された。
鬼ヶ城[おにがじょう] 川前
歴史・観光・行楽
里山の豊かな自然が美しい、アウトドアを満喫できる施設。春は桜やつつじ、夏にはあじさいやラベンダー、秋には紅葉、澄んだ空気の冬には満天の星空など、オールシーズン楽しむことができる。ドッグランもあり。
出典元:いわき市観光サイト
温泉神社[おんせんじんしゃ] 常磐
歴史・観光・行楽
延喜式内磐城七社の一つ。「ゆのじんじゃ」、「ゆぜんさま」とも呼ばれる。祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)。湯ノ岳を神体山とする。社伝によると上古は湯ノ岳山頂に鎮座し、中世には観音山、江戸時代の明和5年(1768)に現在地へ遷宮。本殿は元禄8年(1695)に内藤家により造営され、現在、市の有形文化財に指定されている。
出典元:いわき市観光サイト
海竜の里センター[かいりゅうのさとせんたー] 大久
歴史・観光・行楽
フタバサウルススズキイなどの化石を発見した大久川のほとりにあり、館内には様々な化石が展示されているほか、「いわき市内屋内遊び場いわきっずるんるん」を併設。外ではブラキオサウルスがお出迎え。
出典元:いわき市観光サイト
賢沼ウナギ生息地(沼ノ内弁財天)[かしこぬまうなぎせいそくち(ぬまのうちべんざいてん)] 平
歴史・観光・行楽
底なしでけっして枯れることがないと伝えられてきた賢沼は、殺生を戒める弁財天信仰が結びつき、大鯉や国の天然記念物の大うなぎが生息していると言われている。
出典元:いわき市観光サイト
神白温泉[かじろおんせん] 小名浜
歴史・観光・行楽
不動明王から「神白川を渡った先に湧水がある、それをお湯にして浸かりなさい。」とお告げを受け開湯したという。源泉は、胃腸病や糖尿病などに効くとされる。
蟹洗温泉[かにあらいおんせん] 四倉
歴史・観光・行楽
太平洋を一望できる展望露天風呂、超音波ジェットバスやバイブラバス、寝湯、薬湯風呂など10種のお風呂が楽しめる健康センター。
出典元:いわき市観光サイト
甲塚古墳[かぶとづかこふん] 平
歴史・観光・行楽
古墳時代後期のものとされる円墳。冑を伏せたのに似てることから甲塚という名となったといわれる。かつてはその墳頂に大きな黒松があり「八方にらみの松」と呼ばれていた。
出典元:いわき市観光サイト
神谷村踏切[かべやむらふみきり] 平
歴史・観光・行楽
昭和25年に、神谷村が平市に吸収合併され、村の名前は消えたが、踏切には「神谷村」の名前が残っている。
鎌田橋[かまたばし] 平
歴史・観光・行楽
旧神谷村の大字鎌田と旧平町・平市の字鎌田町を繋ぐ橋。度重なる自然災害による流失や破損、時代の流れによる存続の危機などに見舞われながらも、幹線道路から沿岸の生活を支える道路へ姿をかえ、今に続く。
出典元:いわきの『今むがし』
釜屋[かまや] 平
歴史・観光・行楽
明治39年2月18日の平大火後に、大火に強い蔵づくりの店舗を建築。みごとな総ケヤキの店舗は、大工・左官が百人宰領され、材料にも糸目をつけず時間をかけて作ったもの。「釜屋」は江戸時代の元禄13年創業。磐城平藩御用商人であった初代の諸橋久太郎が、鍋や釜などの金物類を販売し、その後、事業を拡大し、繁盛した。
出典元:「懐郷無限」斎藤伊知郎著
清戸迫横穴[きよとさくおうけつ] 双葉町
歴史・観光・行楽
双葉町立双葉南小学校敷地内に保存されている横穴式装飾古墳。赤色顔料で渦巻文を中心に冠または帽子をかぶった人物2人を配し、その左右に小さく乗馬の人物、弓を射る人、鹿、犬等の動物を描いている。現在判明している彩色壁画の北限である。
出典元:文化遺産オンライン
金冠塚古墳[きんかんづかこふん] 錦
歴史・観光・行楽
直径約28m・高さ約3mの円墳。横穴式石室の中に13体分の人骨のほか金銅製飾金具や玉類、馬具、須恵器などが出土。
草野心平記念文学館[くさのしんぺいきねんぶんがくかん] 小川
歴史・観光・行楽
いわき市の名誉市民でもある詩人 草野心平(1903~1988年)の生涯と作品の魅力を、自筆原稿、詩集、自作朗読音源、そして彼が開いた居酒屋「火の車」の復元展示などで紹介するほか、文学をはじめとした企画展、講演会、演奏会など、多彩な催しを開催。
出典元:公式サイト
草野心平記念文学館[くさのしんぺいぶんがくかん] 小川
歴史・観光・行楽
草野心平の自筆原稿、詩集、自作朗読音源、居酒屋「火の車」の復元展示など、作品の魅力を紹介。企画展、講演会、演奏会などの様々な企画も開催している。
出典元:公式サイト
首切り地蔵[くびきりじぞう] 平
歴史・観光・行楽
小川江筋の整備などし100年以上領土を治めてきた磐城平藩・内藤氏であったが財政難に陥り課税を強化。1738年に大規模な百姓一揆が発生し農民2万人が城下に押し寄せた。しかし、訴えは認められず、指導者7人が鎌田河原で処刑。一方で、大規模な百姓一揆の罰として、内藤氏は延岡藩に移封となった。その後、鎌田河原には村人らによって供養のための「首切り地蔵」(河原子地蔵堂)が建てられた。
クマガイソウ群生地[くまがいそう] 田人
歴史・観光・行楽
田人町石住綱木にある約5万株のクマガイソウの群生地。日本最大級とも言われている。近年、絶滅危惧種であるクマガイソウ。守る会が発足し、手入れや環境整備などをおこなっている。例年5月上旬から咲き始め、下旬ごろまで楽しむことができる。
出典元:いわき市観光サイト
暮らしの伝承郷[くらしのでんしょうごう] 鹿島
歴史・観光・行楽
市内に残っていた茅葺の古民家を移築し、建築当初の状態を復元して展示。年中行事の再現や伝統芸能の実演など、昔の人々の暮らしを今に伝える。
出典元:いわき市観光サイト